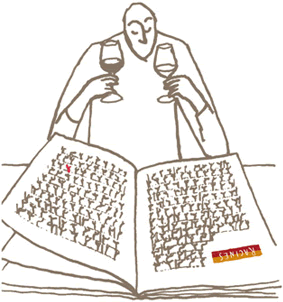ファイン・ワインへの道Vol.108(最終回)
公開日:
:
最終更新日:2025/09/01
寺下 光彦の連載コラム, ライブラリー, 新・連載エッセイ クリスチャン・チダ, エントレ・ペドラシュ, アンリ・ジャイエ, ドメーヌ・ド・ラ・コート, SOYUZ, リヴェッラ・セッラフィーノ, サン・ジュゼッペ, リッジ
一級シャトーは、裸の王様なのでしょうか?
熱波と山火事で、偉大なリアス・バイシャスの50年古木、80年古木の畑などを含む、スペイン全土で計約34万ha(ボルドー全体の約3倍!)が黒焦げになり、ラングドックやコルビエールでも14,000ha(ブルゴーニュ、コート・ドールの約1.7倍)が山火事で焼け焦げ。それでも人々もメディアも、気候変動なんて他人事とばかりに目を背けて何も行動しないこと、しばしば。気候危機はどんどん激甚化し2050年ごろには、地中海沿岸でのワイン生産可能地域が激減するとの研究結果も出る中……。計9年間の連載・最終回に、ふさわしいのか、ふさわしくないのか。当方、40年間ワインを飲み続けての忌憚のない気持ちを、僭越ながら。
目次:
1:富士山も、エベレストも、美しいと思えない理由
2:“基準”になる“新・グランヴァン”は、十分手が届きます
3:世界一のワイン産地は、まだ発見されていないのかも
1:富士山も、エベレストも、美しいと思えない理由
富士山もエベレストも、登ったことがないどころか見たこともない、しかし聞いたことだけはあるという人に、世界の高山の話を聞くと……今ひとつ説得力に欠ける気がしますよね。
この場合、私が思うのは「富士山を見たことないなんてかわいそう」という気持ちでは全くなく。ある日、幸運にも富士山に匹敵するほど高く美しい山に出会っても、”あぁ、なんとなく高い山だなぁ”(でも、富士山って山のほうが高いんだろうなぁ。 有名だし、入山料は高額だし。)と、ぼんやりした(煮え切らない)判断と 感動になるだろう、という点です。
その山が、突如発見された富士山よりはるかに高くて美しい山だったとしても、感動はぼんやり、なのです。実際の富士山を見たことがないために。判断の物差し、いわば判断の“メートル原器”のようなものがその人にできていない、のですね。これは、悲しい話ですよね。
もちろんこれは、ワインについてもあてはまる話です。
最近たびたび「1級シャトーもブルゴーニュのグランクリュも、飲んだことがないんです」とおっしゃる若いソムリエさんにお目にかかりました。 20年前なら「いくつかは飲んでおいた方がいいよぉ」と私も脳天気に屈託なく言ったところでしょう。
しかし今日。一部のワインが株や債券同様の財テク商品化し、価格と”感動の絶対量”が絶望的かつ無慈悲の極み的に合わない残酷世界では……、 若いソムリエさんやワイン・ラヴァ―の勉強用として、 1級シャトーやグランクリュを薦めることは、十分に残忍かつ無責任至極とさえ思えます。
もちろん、ブラインドで同じワインを何種類かの異なる価格情報のみ提示して試飲すると、プロでも高額なワインを有難がるという心理実験は有名ですね。
全く同じワインでも、1本1万円ですと言われると興奮はそこそこ。 1本10万円と言われると大興奮!!、な人がプロにさえいる、 というわけです。人間はかくも弱い生き物なのですねぇ……という話は、今回はさておき。
ならどうすればいいのか? です。
2:“基準”になる“新・グランヴァン”は、十分手が届きます
1級シャトーや中途半端なグランクリュを試す前に、それに限りなく近い、時には超えているとさえ思えるワイン、いわば”隠れたグランヴァン”、“新グランヴァン”を、広い地球の隅々から真面目に探し、ワイン評価の基軸、“ワイン版メートル原器”にすること、しかないように思います。
電灯も自動車も全くなかった時代、1855年にできたボルドー格付けから170年め。
現在の地球には、確実にあります。そんなワインが。
昔のアンリ・ジャイエ1級くらいの価格(1~2万円少々)で。隠れた、知る人のみ知るグランヴァンが(昔のジャイエも、そんな感じでしたよ)。
それは例えば、
●ドメーヌ・ド・ラ・コート/ラ・コート ピノ・ノワール
トップ・ブルゴーニュに匹敵するゴージャス&セクシー・アロマの爆発感。
●エントレ・ペドラシュ/ピコ・アリント・ドシュ・アソーレス
コシュ=デュリを彷彿とさせる、酸とミネラルの大彫刻の趣。
●リヴェッラ・セラフィーノ/バルバレスコ・モンテステファノ
15年以上の熟成で、ネッビオーロの域を越え、世界最高峰の赤の一つに数えられる深遠さに到達。
●クリスチャン・チダ/ノン・トラディション
巨大な教会の内部に足を踏み入れたような、神聖な波動感。
●サン・ジュゼッペ/ロッソ・ディ・モンタルチーノ
多くの有名ブルネッロを凌駕。もちろん同社のブルネッロも壮麗度が異次元。
おっと、それでもどうしてもカベルネ・ソーヴィニヨン、という方には酸化防止剤は多いですが、
●リッジ/モンテ・ベッロ
飲む・長編小説。このワインがオーパス・ワンの約半額なのは、ロールス・ロイスがクラウンの半額、という感じ。
他にも多いですが、今日はその一例、ということで。
いずれも それぞれ、倍どころか 10倍以上の価格のワインさえ凌駕する、 世界のトップ・グランヴァンそのものだと私は考えます。
例えば、ここにあげた「ピノ・ノワール ラ・コート」は本当に 1本50万円クラスのブルゴーニュと差があったとしても、極々わずかだと思うのです。
若いソムリエさんやワイン・ラヴァ―の方々には、心から、「その極々わずかな差のために、プラス 48万円を工面する必要ないと思いますよ」 と申し上げたい気持ちです。
上記ワイン全て、権威的格付ワインの代替としての、ワイン 評価の基軸、 すなわち富士山やエベレスト(に近い山)の役割を十分に果たすと思います。
若い方々、上記のワインを飲まれたら、十分エベレストに“近い”山に登ったこと、になります。「1級シャトーやグランクリュに負けない、世界のトップワインを飲んだぞ!」と胸を張ってください。ぜひ、堂々とね。
そこまで言うために……。筆者は40年間、ペトリュス(含:1982、1961)、DRC(含:コンティ1952、1954、1972)、ジャイエ1級(含:一人で1本飲み7回)、そのほか1級シャトー(含:1929、1945、1961)合計、ゆうに200本以上は謙虚に試飲した上で……。
相対的なワイン価値評価軸は、やっと先週あたりから、身についてきたような気がします(勘違いかも、ですが)。
世の中に絶対はない、と言いますが、本当に。50万円のワインが5万円のワインの10倍・感動的、なんてことは絶対、ないように思いますね。あったとしても、その差は極極々わずか。むしろ、逆のケースさえあるかと思いますよ。本当に。
3:世界一のワイン産地は、まだ発見されていないのかも。
そしてもう一点、重要なのは、サッと挙げた上記のワインのうち2本は、大西洋、ポルトガル領離島・ピコ島や、オーストリアのブルゲンラントなど、20世紀には”真のグランヴァン産地”の候補には間違えてもならなかった、非・有名産地、非・権威的産地から生まれてきているという点です。前世紀と比べて、地球各地にはグランヴァンの産地が確実に、大きく“増加している”のです。このことは、大いに重視すべき点でしょう。
これからも。
いわゆるエスタブリッシュメント産地(有名・権威的産地)以外から未知のグランヴァンが、まさに新しい天体が生まれるように、現れてくれることでしょう。
そんな2025年。21世紀のもう1/4が終わった今、いつまでも前世紀にがっちり焼き印を押されたワイン産地のカースト的上下観に縛られていては、本当に“損”、ですよね(フランス人はよくこういう時に、“先入観の奴隷”という言い方をしますね)。
西暦2030年か、2040年ごろなのか。想像もしなかったワインが、想像もしなかった地域から、今以上に日本に届いているかもしれません。その偉大さを正しく判断するためにも、日々、開かれた澄んだ心で、ワインに向き合いたいものですね。
地球はまだまだ広いです。“世界一のワイン産地”は、今もまだ確定していないのかもしれませんよ。
では、そんなエベレスト(級)ワインを見つけたら、またどこかでご報告させていただきます。その日まで、しばらく、ごきげんよう。
謝辞:
9年もの長きにわたり、貴重な機会を賜り、時には踏み込みすぎた拙稿をご容認いただいたラシーヌ、合田泰子様と塚原正章様、およびスタッフの皆様のご厚情に心から感謝いたします。
バローロ現地取材で5日がかりで400種類のネッビオーロを試飲したのに、一番衝撃的だったワインが取材以外で出たラシーヌさん扱いのネッビオーロだったり。オーストリア現地取材で約200種を試飲したのに、それより何倍も衝撃的だったワインが、取材外のラシーヌさん扱いのオーストリアワインだった、といった体験が、お世辞でなく無数にありました。
合田様・塚原様が厳選されたワインは、常に私の蒙を啓き続けてくれました。
この場をお借りしまして、心より御礼申し上げます。有難うございました。
追伸:
ラシーヌ様への畏敬は最大限、抱いていますが、本連載中で推挙したワインや生産者は、連載1回目から108回目まで、一切の忖度や便宜はありません。全て、あくまで個人的な視点で~どこまで中立的でありえたかはべつとして~ワインを推挙さていただいていることは、再度、改めて読者の皆様にはお伝えさせてください。
今月の、ワインが美味しくなる音楽:
(ワイン同様)未知の地から、偉大な作品。
ベラルーシの、ブラジリアン。
『Krok』SOYUZ
過去107回、ご紹介したこのコーナーのベスト・オブ・ベストとして、ブラジルの楽聖「カルト―ラ」を再度、推させていただこうと思っていた矢先……。突如、ベラルーシ(!)から。流麗、メロウ、スウィートなブラジリアン・ユニットが現れ、驚き、ご紹介です。首都ミンスクを拠点に、サン・パウロで録音されたこのアルバム、チン・ベルナンデスなど現地の大物もゲストに迎え、淡いサウダージがたまらない極上のトラックは、まさかベラルーシ発とは思えない域。ワインと同様に……、素晴らしい作品は“既定の有名産地”以外からも堂々と生まれるのだなぁと教えてくれる啓蒙力も、ありがたい限りです。聞けば、広がる音選びの視野と視点。それもなんとも。爽快ですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=GqdwkjHNAK8
今月のワインの言葉:
「ワインとは、飲む名画であり、飲む名曲である」
寺下光彦
寺下光彦
ワイン/フード・ジャーナリスト
「(旧)ヴィノテーク」、「BRUTUS」、「MEETS REGIONAL」等に長年ワイン関連記
事を寄稿。アカデミー・デュ・ヴァン 大阪校」、自然派ワイン、および40年以上熟
成イタリア・ワイン、各クラス講師。イタリア、ヴィニタリーのワイン品評会・審査
員の経歴も。音楽関連記事も「MUSIC MAGAZINE」に約20年、連載した。
- PREV ファイン・ワインへの道Vol.107