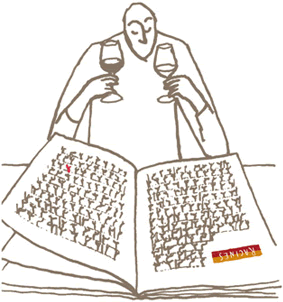ファイン・ワインへの道Vol.107
公開日:
:
寺下 光彦の連載コラム, ライブラリー, 新・連載エッセイ ドメーヌ・ジョベール, ローヌ, ミゲル・メリーノ, ボジョレ, Yaima Orozco&Migue de la Rosa, 太宰治, リオハ
リオハは白⁉ 赤産地の白推し現象の蠱惑。
重厚なステーキのお店と信じ込んでいたら、意外にも白身魚のお刺身や椀物の出汁が美味しく、 魚とお椀ものを目当てにそのお店に通うようになってしまった……という感じでしょうか?
一般に赤ワインの王国とされる産地で、白ワインに注力し、生産量の点でも 白を増強していこうという推し現象が少しずつ目立ってきました。 世界的に赤ワインの消費の減衰傾向が続き、白ワイン消費が伸びているというマーケティング上の理由ももちろん要因だと思われますが……、 それだけで片付けるには勿体ない、赤の有名産地の白について考察してみました。
目次:
1:リオハの白は、”電気的でシャープ”(?)
2:ボジョレでも、白(シャルドネ)生産をブーストへ
3:ローヌ委員会の大規模プロモーションでも……。
1:リオハの白は、”電気的でシャープ”(?)
「リオハは数年後には赤ワインと同じぐらい、白ワインでも世界に知られるようになると思います! この土地は 今後、今まで以上に素晴らしい白ワインを産むためのブドウ品種とテロワールがしっかりと備わっているのです」。
そう勇ましく宣言してくれたのが、リオハ・アルタの中心部、ブリオネスを拠点とするボデガス・ミゲル・メリーノの当主、ミゲル・メリーノJr.さん。 言うまでもなく 赤ワインの帝国と考えられてきたリオハで、2016年に家族のワイナリーを引き継いだ時から
「白ワインの重要性とこの地での品質はますます高まっており、7種類の赤ワイン以外に、白も重視し注力してきました。そして 現在、DOCaリオハ委員会も、白品種の栽培を推奨していることもあり、今後、リオハ全体での白ワインの生産量はさらに増加することは間違いありません」と語ってくれました。
もちろん 今回、この稿に着手したのは 生産量面からではなく、見逃せない( 見逃すと損、しかも大きな、と思える)その品質の高さゆえ。 そこを実感させてくれたのが 、彼が手がけたミゲル・メリーノ・ブランコ2022。
ビウラ(=マカベオ)とガルナッチャ・ブランカのブレンドによる、傑出した華やぎあるレモンピール、アカシア、ほのかなアーモンド香と、気品輝く酸とミネラルの引き締まった美しい彫刻とも思えるストラクチャーは、ある意味で美術品のよう。
さらに、長い余韻の中に優しく響くテンションの奥に感じさせる、澄んだ精神性にも心を奪われる、堂々のグランヴァンだったのです。
その高品質の理由を、ミゲル・メリーノJr.さんに尋ねると「最重要なのは、伝統的に量産品種と考えられたビウラの低収穫を徹底すること。ビウラは、特に古木で低収量を一貫した場合には、非常に エレガントな白ワインを生む品種。加えて我々の土地、ブリオネスに顕著な昼夜の寒暖差と、豊富な石灰岩、そして 有機栽培も重要です。そのことにより、私たちの白の“電気的でシャープな”味わいが生まれるのです」と語ってくれました。
“電気的でシャープな”という表現は、なかなかにスペイン人的なユニークさを感じさせるものですが 、あのリオハからそんなスタイルの白が生まれると 、想像できた人はそう多くないことでしょう。
だからこそ、日々の探求が楽しく、ワインの楽しみの地平と宇宙は、無辺なのですね。
ボデガス・ミゲル・メリーノ ガルナッチャ・ブランカの畑
ちなみにリオハDOCa 委員会のホセ・ルイス・ラプエンテ事務局長によると、リオハ全体の白ワイン比率は 過去10年で2倍近くに増加。 2024年は全体の11.3%となり、 10年前と比べて 5%上昇、とのこと。
また、ボデガス・ラモン・ビルバオの醸造責任者ロドルフォ・バスティーダ・カロ氏によると、リオハ の生産量はかつては 赤と白が均等で、1600年代のリオハの最も古い記録に記述されているのは 白品種であるマトゥラナ・ブランカ(Maturana Blanca)であることを挙げ、この地の白ワインの伝統性に言及しています。
この、マトゥラナ・ブランカという品種に関してはミゲル氏 も注目しており「ガルナッチャ・ブランカ、マトゥラナ・ブランカ、マルヴァジア、テンプラニーニョ・ブランコなどの品種はさらに向上の余地がある。 私たちは白に関するブドウ、土壌、 技術をまだ知り始めたばかりです。知見の蓄積と向上により、 近い将来 さらに素晴らしい白ワインができるはずです」と、リオハの白の未来像を高らかに、自信たっぷりに語ってくれました。
2:ボジョレでも、白(シャルドネ)生産をブーストへ
もう1箇所、昨今”白ワイン推し”を掲げる赤ワインの地といえば、ボジョレもまた。昨年12月、新しくボジョレ・ワイン委員会の事務局長に就任したオリヴィエ・バドゥーロ氏 が就任早々、野心的に掲げたビジョンは、
「今後10年以内に白ワインの生産を現在の3倍に。 現在の全体の4%から12%に引き上げる」というもの。
この未来図は多分に、現在の世界マーケットの白ワイン隆盛に対応したもののよう。そんな中、
「ボジョレは常にワイン品質向上に取り組んでおり、 品質向上への努力は決して止まることはありません。 例えば 近年、ボジョレのブドウ畑全域に計 1万6000個の縦穴を掘って 地質調査を 行いました。 その中でボジョレ南部に特徴的な、”ピエール ・ドレ(黄金の石)”という土壌がシャルドネ に特に好適だということが発見できました。
粘土と石灰岩が混ざり合ったこの土壌により、軽やかでフレッシュなだけではない、奥行きあるボジョレの魅力を持ったシャルドネ が生まれるのです」と語っています。
もちろんオリヴィエ氏がボジョレの白をブーストしようとする 以前から、 この地のシャルドネ はブルゴーニュ・ブランとして、また クレマン・ド・ブルゴーニュの大切な素材として世界のマーケットに運ばれてきました。その素朴でのどかな個性の“見逃せなさ”を知るには、例えば
ドメーヌ・ジョベール2022ブルゴーニュ・ブランなどを開けてみると……、おだやかな洋梨、ユズ、セルフィーユの香りと、カドが丸く、不思議とほっこりさせてくれる優しい酸とミネラルの質感で、「ボジョレのシャルドネ、スルーするには勿体ない」と、きっと思えることでしょう。いえ、すでにその穏やかな魅力は、本稿お読みの方々は既にご存じ、かもですね。
3:ローヌ委員会の大規模プロモーションでも……。
さらにこの夏には。ローヌワイン委員会がヨーロッパ主要国とアメリカ、カナダで行ったプロモーションイベントは、超・直球的に「 ローヌ・イン・ホワイト」がテーマ。ローヌで、白のみがプッシュされました。
ローヌワイン委員会会長のフィリップ・ペラトン氏いわく
「ローヌ渓谷を世界有数の白ワイン産地の一つに位置付ける ことを目標としている」とのこと。現在、ローヌの白比率は2024年 ヴィンテッジで全体の12%。 委員会は今後も「 白の売上の着実な増加が見込まれる」と自信を見せています。
ともあれ、 長い目で見ると。トスカーナの モンタルチーノは150年少々前までは、白の甘口ワインの産地で、現在の栄えあるモンタルチーノの名前から赤ワインを想像する人は、当時は皆無だったとのこと。 ロワールのサンセールは、 フィロキセラ前まではピノ・ノワールとガメィの赤が大半で、白は少数派だったそう。聖なるバローロ、バルバレスコのお膝元、ランゲ周辺では、絶滅寸前だった土着品種の白、ティモラッソを ロアーニャなど多くの気鋭生産者が復興し、素晴らしいワインを生んでいるのはご存じの通り、ですね。
もちろん、なにもそこまで ドラスティックな変化ではなくとも。
赤ワインの王国と思われていた地域での白、 もしくは 逆に白ワインの聖地と思われていた地域での赤を新しく見かけたら……。 イロモノ、とかキワモノ、 なんて思わずにアタックされると……未知の新しい景色が、舌と心に広がるかもしれません。
そんな新しい、”美味しさと感動の新大陸”の発見こそ、ワインの大きな楽しみの一つだと思いますが……。皆さんは、いかがですか?
今月の、ワインが美味しくなる音楽:
キューバ版ボサ・ノヴァ?
“フィーリン”の心を継ぐ、夏の夕風のような“チル・アコ”。
『Debo dejar』 Yaima Orozco&Migue de la Rosa
8月は、チル・アコ・キューバ音楽ですね。チル・アコとは、もちろんチル&アコースティックのこと。キューバこそ、その聖地です(ダンス・トラックばかりではなく)。特にこの季節、まるで海沿いの道にサッと吹く、夏の夕風のようなこのアーティストのアコースティック・ギターと女性ヴォーカルは至福の涼感、そのものです。
1950年代末に生まれ、キューバ版ボサ・ノヴァとも言われる音ジャンル“フィーリン”のクールネスを現代に受け継ぐこのアーティスト、ヤイマ・オロスコ。素朴さと洗練が静けさの中に自然に溶け合う曲調と、アルザスのオフ・ドライワインのような(後味が極々ほのかに甘い)美声がなんとも印象的なのです。暑さがピークのこの時期、オフ・タイムに味わう冷た~いワインにペアリングして聴くと、心と頭の隅々まで。クール・ダウンできますよ。しみじみと。ほっこりと。
https://www.youtube.com/watch?v=nbIY5PKf_r4
今月のワインの言葉:
「常識は、十年ごとに飛躍する」
太宰治
寺下光彦
ワイン/フード・ジャーナリスト
「(旧)ヴィノテーク」、「BRUTUS」、「MEETS REGIONAL」等に長年ワイン関連記
事を寄稿。アカデミー・デュ・ヴァン 大阪校」、自然派ワイン、および40年以上熟
成イタリア・ワイン、各クラス講師。イタリア、ヴィニタリーのワイン品評会・審査
員の経歴も。音楽関連記事も「MUSIC MAGAZINE」に約20年、連載した。
- PREV ファイン・ワインへの道Vol.106
- NEXT ファイン・ワインへの道Vol.108(最終回)